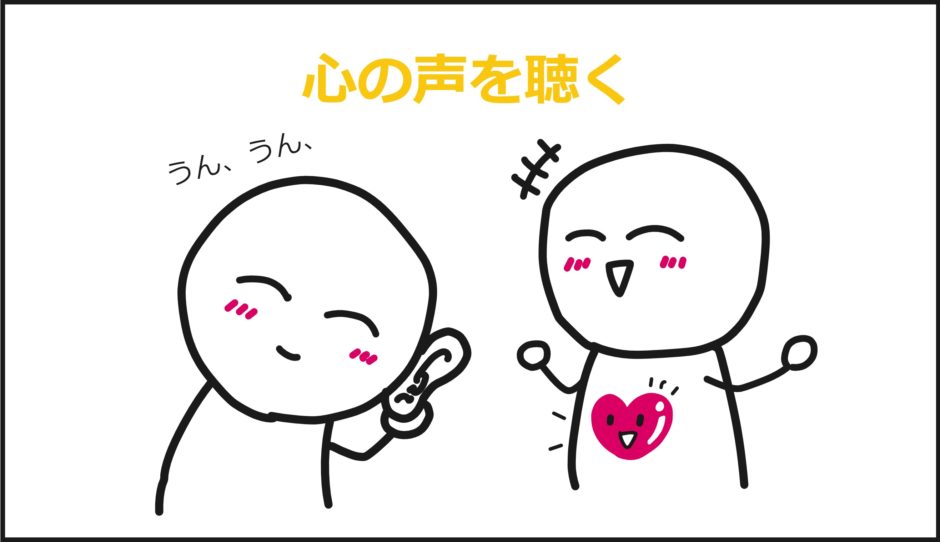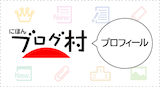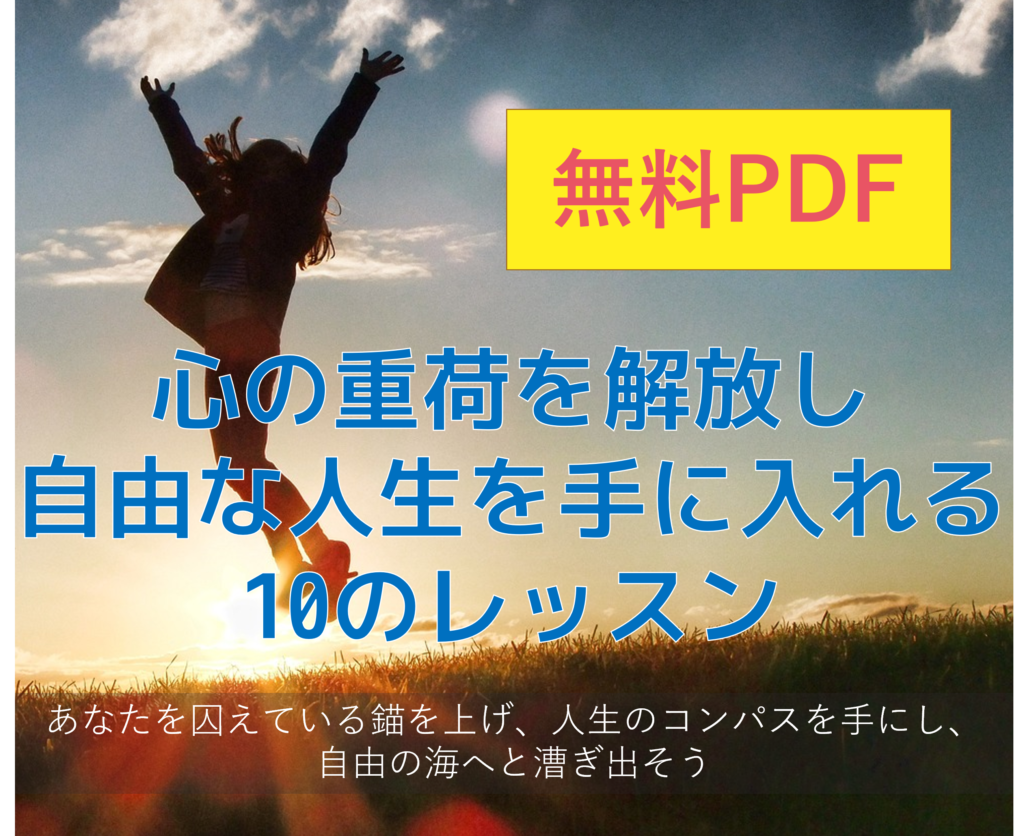「本当に相手の話を聴けていますか?」
忙しい日常で、多くの人が「聴く」ことの真実を見失っています。
会話の中で、私たちがしばしば落とし穴に陥るのは、相手の話を聴くフリをしながら、実は自分の考えや返答に頭を使ってしまうこと。
では、如何にして心からの理解に徹し、真のコミュニケーションを築くことができるのでしょうか。
本文ではその解決策を考察します。
バックトラッキングに潜むリスク
「傾聴」において一般的な手法として「相手の言葉を繰り返す」があります。
この技術は心理学のNLP(神経言語プログラミング)において「バックトラッキング」と称され、相手の言葉を単純に繰り返すことで信頼関係を築く手段として紹介されています。
しかし、傾聴は単なるテクニックではありません。
もし傾聴をバックトラッキングを使ったテクニックとしてしまうと、不測のリスクが伴います。
例えば、「実際には聴く気がない」状態で行われるバックトラッキングは、その無関心さが無意識に相手に伝わる可能性があります。
一般的なケースとして多く見受けられるのは「ながら聴き」です。
TVやパソコン、スマホを操作しながら、「うんうん、◯◯なんだね」と相槌を打つ行為です。
また、別のことを考えながら聞いてしまうこともあります。
これらの行為は、無意識に伝わる以上に、無関心さが態度に表れてしまいます。
聴く気のないバックトラッキングは、傾聴を心を込めなくても出来るただのテクニックに成り下げます。
信頼関係を築くという目的から逸れ、かえって信頼を失墜させる結果を招く可能性があります。
バックトラッキングを行うから信頼関係が築きやすくなるわけではありません。
答えるために聞くのではなく、理解するために聴く
「聴く」という行為だけを切り取った時、それは何のために行われるのでしょうか。
多くの人は「どのような返答をするか」を考えながら聞いています。
つまり、「答えるため」に聴いているのです。
しかし、答えを準備する過程では、自分が持つ知識や経験から適切な回答を探すため、脳のリソースを集中的に使います。
人間の脳は一度に多くの情報を処理する能力が限られています。
脳は複数のことを同時に処理しているようで、実は1つの処理を高速に切替えているだけだそうです。
その結果、相手の言葉に耳を傾けていると思っていても、実際にはその内容を完全には処理しきれていません。
瞬間的なことではありますが、その一瞬で聞き逃したり、誤解したりする可能性が高まります。
針飛びするレコードのように、相手の声が飛ぶと同時に、それはコミュニケーションの雑音にもなります。
「何て答えを返そうか考えながら」聞くことは、実は私たちが最も聴いているつもりになっている「ながら聴き」なのです。
そもそも答えを返すプロセスは単純化すれば、以下のようになるでしょう。
- 相手の話を聴く
- 相手の話を理解する
- 自分の意見や回答を考える
- 相手に返答する
「どのような返答をするか」考えながら聞くことは、「2. 相手の話を理解する」が断片的になります。
これは診断途中で医者が病状を断定するようなものです。
診断ミスが生じる可能性は低くとも、小さな見落としが重大な結果を招く可能性があります。
だからこそ、真の「傾聴」を行うには「理解すること」に焦点を合わせるべきです。
答えるために聞くのではなく、理解するために聴きましょう。
言葉だけではなく、心を傾聴する
それでは、理解に徹するためにはどうすればよいのでしょうか。
やはり、バックトラッキングが一つの有効な手段となります。
話の終わりに理解度をテストしますと言われた場合、私たちは話を聴く意識が変わります。
同様に、相手の話をバックトラッキング「だけ」しようと考えるだけで、話の理解度は高まります。
何も気の利いたことを言わなくても良いのです。
知識をひけらかす必要も、引用や複雑な言葉を使う必要もありません。
重要なのは、ただ相手の言葉を繰り返すことです。
そして、さらにバックトラッキングの効果を高めるには、もう一つの要素があります。
それは、相手に「愛ある態度」で接することです。
「愛ある態度」とは赤ちゃんに接する時のような態度です。
よちよち歩きを始めたら、頑張って歩こうとしている姿をただ見守りますよね。
片言で話し始めたら、間違いを正さず、ただただ「うん、うん」と話し終わるまで聴きますよね。
「もっと手足をこう動かしなさい」とか「その言い方は違うぞ」とは言いませんよね。
無用なアドバイスや手助けはせず、ただ見守るでしょう。
幼い子供が「見て、白い車!」と言ったら、「白い車だね」と答えるでしょう。
「だから何?」とは追求しません。
しかし、相手が大人だと、「だから何?」という態度になることがよくあります。
思春期の子供や部下に対して「そんなことより◯◯はどうした」と、自分が聞きたいことに話を変えがちになります。
そのような態度では、相手の本当の気持ちを理解することはできません。
そうではなく、相手は何に興味を持っているのか、何に困っているのか、どんな感情を抱いているのかに関心を持ちましょう。
相手の表面的な言葉だけでなく、その奥に潜む感情や願望に関心を持ちましょう。
そして、そこから感じ取ったことをバックトラッキングに反映させるのです。
「楽しそうだね」や「困っているんだね」など、あなたが感じ取ったことを加えると、相手はあなたが真剣に聞いていると感じるでしょう。
相手の話を聴くという行為は、相手の言葉だけでなく、相手の心を傾聴することが求められているのです。
しかし、自分が感じ取ったことが実際とは異なると、相手は理解されていないと感じてしまいます。
そのため、真剣に理解を深めようとする姿勢が重要になるのです。
傾聴はテクニックではなく「あり方」です。
あなたがどのような気持ちで相手の話を聴くかが問われる行為です。
テクニックに頼るのではなく、「愛ある態度」で相手の心を理解する努力をしましょう。
そこには上手いも下手もありません。
ただ、相手に対するあなたのあり方があるだけです。
今日、あなたは誰の心を傾聴しますか?
 Life Quest Alliance
Life Quest Alliance