「無理」
他人に対しても自分に対しても、人生の中で幾度となく使ってきた言葉ではないでしょうか。
他人から言われたこともあるかと思います。
自分に使えば、唱えるだけで、何もしなくて良くなり楽になる言葉。
他人に使えば、その人の自信と可能性を奪ってしまう言葉。
以前、友人のFacebookにシェアされた植松努さんのTEDxSapporo 2014の動画を拝見していました。
そして先日、NLPマスタープラクティショナーコースでも紹介され、再度観る機会を得ました。
改めて良い内容だなぁと思いましたので、ログとして残しておこうと思います。
植松さんは北海道にある株式会社植松電機 代表取締役だそうです。
小さい頃から宇宙にあこがれ、周囲から無理だと言われながらも、北海道大学の永田教授とともに宇宙開発に関連する様々な研究成果をあげている凄い人です。
今回のTEDでは人の自信を奪ってしまう「どうせ無理」を根絶して、世の中からいじめや虐待をなくしていきたいという話をされています。
読んでいませんが関連する書籍もあるようです。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/027073ef.6eb0d443.03b43aff.b16dfbc2/?me_id=1213310&item_id=13306418&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7525%2F9784887597525.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7525%2F9784887597525.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext) | NASAより宇宙に近い町工場 僕らのロケットが飛んだ [ 植松 努 ] 価格:1430円(税込、送料無料) (2019/11/13時点) |
子供が親を愛する感情を感じ取ろう
動画の中で、植松さんが児童施設へボランティアに行った時のことを話されています。
その中で、親から虐待を受けた男の子が植松さんに語った夢は、
親ともう一度暮らすこと
植松さん自身も衝撃を受けたと語っていますが、私も衝撃を受けました。
どんなにひどいことをされても、子供は親を愛しているものなんだなと。
「親の心子知らず」ということわざがあります。
親の愛情を子供はわかっていない、親にならないとわからないという意味合いで使われます。
しかし、親が「子供の世話は大変」と思う時は、ともすれば、世間一般、社会一般の常識の枠に子供を当てはめようとしている可能性もあります。
もちろん、この社会の中で暮らしていくためには必要な知識や礼儀作法がありますので、子供が困らないためのしつけは大事です。
ただ、植松さんが最後の方で仰っていた
教育とは、死に至らない失敗を安全に経験させるもの
という言葉から、人様に迷惑をかけない範囲で温かく見守るのも親心かなと思いました。
また、本当にわかっていないのは親の方かもしれません。
子供の親に対する愛情の深さは、この児童施設の子供に限った話ではないのではないでしょうか。
虐待されて死に至ってしまう子供たちの事件が後を絶ちません。
子供たちは物理的に死ぬまで親元を逃げられないのかもしれません。
しかし、もしかしたら、どんなことをされても親を愛しているから逃げないのかもしれないと思ってしまいました。
子供の純粋な愛情を親が感じ取ることができたら、虐待はなくなるのかもしれません。
子の心親は知るべし
ということを、心掛けていきたいなぁと思いました。
認めることが着飾る必要のない世界を創る
植松さんは、自信を無くした人たちは他人を害するようになるとおっしゃっています。
- お金で自信を買う
- 身を飾るようになる
- それを自慢する
- 人を見下し
- 他人に努力されたら困るから邪魔をする
「能ある鷹は爪を隠す」とあります。
能力のある人、自分に自信のある人はわざわざそれを周りに見せびらかす必要がありません。
自分に自信が無いからこそ、自分の強さや能力、身なりを周りにアピールして認めてもらわないと安心できないのでしょう。
それが、周りからポジティブにとらえられるか、ネガティブかは関係なく。
動画の中でアフリカから来た人たちの話をされていますが、できないから、生み出せないから、暴力やウソに頼って他人から奪うしかなくなるのだと。
一方で、人は足らないから助け合えるんだとおっしゃっています。
中途半端であっても、ちょっとでもできるだけマシなんだと。
人の足らないところ、できないところに焦点を当てて「どうせ無理」と自信を奪ってしまうと、着飾る人や奪う人を生み出してしまいます。
それよりも、
少しでもできているところを認め、
その人が今持っている能力を認め、
その人のありのままの姿を認める
自信を与えることで、無理に着飾る必要のない素の自分を素晴らしいと自他ともに認められる世界を創る方が良いでしょう。
応援する人になるための「だったらこうしてみたら」
植松さんは「どうせ無理」の言葉を、
- 人の自信と可能性を奪ってしまう言葉
- 唱えるだけで何もしなくて済む、楽になれる言葉
とおっしゃっています。
植松さん自身も小学校の先生に「どうせ無理」と言われて自信を無くし、一時期夢をあきらめていたそうです。
日本の将来を担っていく子供たちの可能性を教師が狭めてしまうこと自体驚きですが、右にならえでサラリーマンをしていれば生きていくに困らないという社会の中で、まずは平均的であることを優先させた結果なのかもしれません。
現在は終身雇用もなくなり、会社への帰属意識も小さくなってきています。
世界が激動する中で、サラリーマンや公務員であることが安定している時代ではなくなっています。
そのような状況の中では平均的な人材を育ててしまう「どうせ無理」という言葉は死語にしてしまうのが良いでしょう。
植松さんは「どうせ無理」の代わりに
「だったらこうしてみたら」
を推奨しています。
子供が夢を語ったとき、
難しい課題に悩み相談してきたとき、
チャレンジしたけどうまく行かなかったとき、
大人は子供の可能性を奪うのではなく、「だったらこうしてみたら」と寄り添ってみましょう。
「いいね、できるよ」と応援してあげましょう。
それは、私たち自身が「奪う人」にならないための大切な言葉でもありますから。
人の慣れの力は侮れないものがあります。
ある言葉を使い続けると、その言葉を使うことに長け、何に対してもその言葉がまず頭に浮かぶようになります。
「無理」を使い続ければ、未知のモノ、ちょっとでもチャレンジングなモノに出会った場合、まず「無理、無理」と反応してしまいます。
同様に、自分に対しても他人に対しても
だったらこうしてみたら?
を使い続けたらどうなるでしょうか。
きっと様々な可能性に目が向き始めることでしょう。
あなたの人生を今よりももっと豊かにしていくために、これからどんな言葉に慣れていきますか?
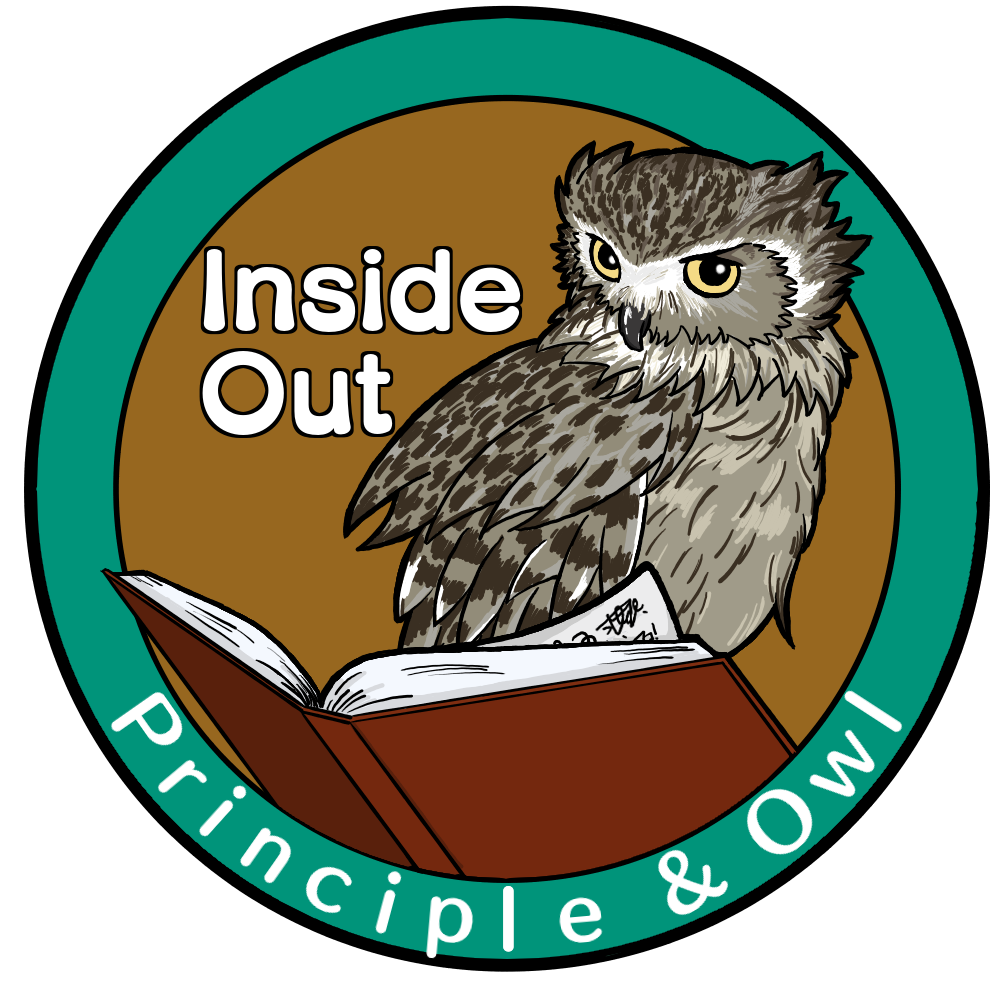 Be Highly Effective Person
Be Highly Effective Person 

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/027073ef.6eb0d443.03b43aff.b16dfbc2/?me_id=1213310&item_id=16589183&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0246%2F9784863940246.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0246%2F9784863940246.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

