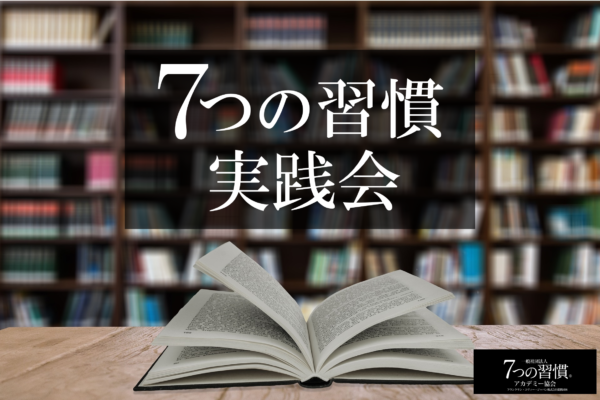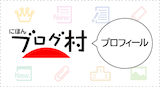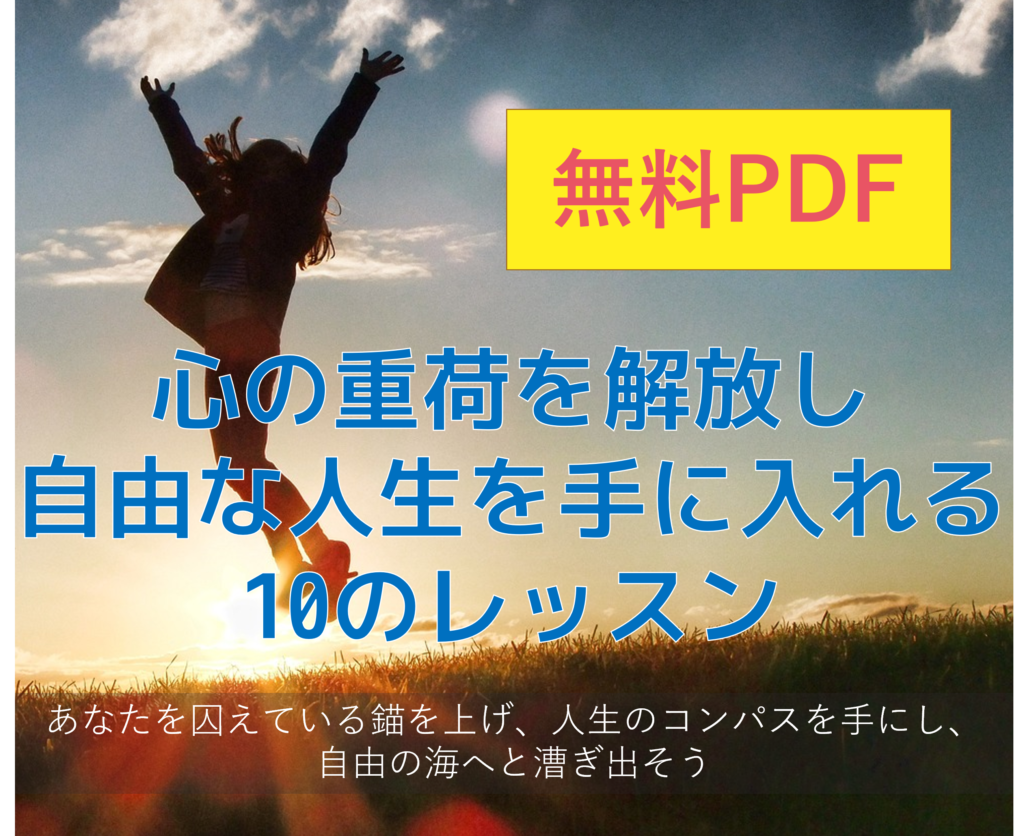皆さーん、イライラしていますかー?
誰かと話をしているときに、イライラを感じることはよくあります。
相手に対して「どうしてこういう風に考えるのだろう?」とか、「いったい何の話?」と思うことも。
相手のネガティブな言動や、他人に対する不満、また、自分は悪くないし困っているといった「嫌なあの人、可哀想な私」話は、聴いている方としては正直うんざりします。
これらは過去にとらわれ、自分ではない誰かが変わることに解決を見出そうとしており、話し手が一時的にスッキリするだけで、解決に至ることは少ないからです。
こういう話をする人の多くは、原因を自分の外側に置いています。
スティーブン・R・コヴィー博士の『7つの習慣』で言えば、「関心の輪」に意識を向けているということ。
関心の輪とは、懸念することから興味あることまでの広くさまざまな関心事のことを言います。
自分のことだけでなく、職場や家族のこと、社会問題、政治、国際紛争、天気など、ありとあらゆる関心事が含まれます。
当然、この中には自分でコントロールできないものが多く含まれます。
自分でコントロールできないものに対して不平不満を漏らす人たちは、この関心の輪に意識が向いており、自分でコントロールできないものを変えたいと切に願っているのです。
一方、このような不平不満が少ない人は、自分でコントロールでき、影響を与えられるものに意識を向けています。
この領域を「影響の輪」と言います。
関心の輪に入る関心事の中から、自分にコントロールできることだけを選び取ったものです。
自分でコントロールできることに集中しているため、結果も自分次第となり、不平不満は少なくなっていきます。
つまり、周囲に対する不満を軽減するためには「主体性」を持つことが必要になるのです。
主体性を持たなければ行けないのは、私
そうすると、私たちが誰かと話をするときのイライラを解消するには、不平不満を言ってくる人たちが自ら主体性を持ち、影響の輪に集中すれば良いことになります。
「そんなこと言っていても始まらないでしょ。自分にできることに意識を向けてみなよ」と伝えればよいでしょうか。
ところが、これでは相手が変わるまで、私たちは我慢をしながら待たなければいけません。
また、これは私たちの不満を解消するために、相手が変わることを期待していることにもなります。
これだといつの間にか、相手の「嫌なあの人、可哀想な私」話が、自分のことになってしまいます。
どんなに優れた見識や経験を持っていて、それが組織や社会の価値観と合致していたとしても、それを相手に押し付け、変わることを期待したとき、私たちは主体性を欠いてしまうのです。
相手がどんな人であれ、どんな不平不満を伝えてきたとしても、私たち自身が主体的であり、自分でコントロールできることに意識を向ける必要があるのです。
不平不満ではなく根本原因を明らかにする
それでは、私たちが主体性を持って、不平不満を言う相手に対峙するにはどうしたらよいでしょうか。
そもそも、私たちが不平不満に対してイライラする原因の一つは、それを聴いても、解決してあげられないどうしようもないことだからです。
相手の影響の輪にないことは、その人にはコントロールできないことだからです。
もちろん、聴く側の影響の輪に入ることはあるかもしれません。
例えば、部下にはどうしようもないことでも、上司の権限で処理できることはたくさんあります。
しかし、目の前の個々の事象は解消できても、原因となるものが変わっていなければ、問題は再発します。
つまり、私たちが行うべきことは、代わりに問題を解決してあげることではなく、
相手の不平不満の根本原因を一緒に突き止め、それに対処できるようサポートしてあげる
ことになります。
それには、『7つの習慣』の第5の習慣「まず理解に徹し、そして理解される」にあるように、相手を理解することから始めなければなりません。
近しい人の相談には応えたくなってしまう
しかし、私たちは相手の相談に乗った際、その人の問題を解決してあげたい、もしくは解決しなければと考えてしまいます。
私たちはえてして、問題が起きると慌ててしまい、その場で何か良いアドバイスをしてすぐに解決しようとする。しかし、その際私たちはしばしば診断するのを怠ってしまう。まず、問題をきちんと理解せずに解決しようとするのである。
『7つの習慣』
これは自分に近しい人であればある程、その傾向は強まります。
職場の人や友人などの相談であれば、最後は「がんばって」で終わらせることもできます。
しかし、家族、特に子供から相談を受けた場合は、何とかその状況を解決に導いてあげたいと思ってしまいがちです。
そのようにして、不平不満を並べていないで、どう解決できるかを考える方向に話を持っていってしまい、暗に相手に変化を求めてしまうことになるのです。
コーチングやカウンセリングなどが、家族にはできないと言われる所以です。
「診断を信用できなければ、処方も信用できない1」のです。
何とかしてあげたい気持ちを抑えながら、相手の不平不満の裏にある根本原因を、まず理解することが大切です。
相手を理解するには覚悟がいる
しかし、相手の不平不満を聴き、理解に徹することは非常に難しいことです。
前述の解決してあげたくなる欲求を抑えることもそうですが、相手の話を聴くことで、自分のやり方や意見を変えなければいけないと思うと、私たちは自己防衛体制に入ってしまうからです。
自分の考え・気持ちを抑え、相手の考えを100%素直に受け入れることは正直怖いものです。
しかし、『7つの習慣』では、相手を理解するには傷つく覚悟が必要であると述べられています。
相手の話を深く聴くには、強い安定性が必要になる。自分自身が心を開くことによって、相手から影響を受けるからだ。傷つくこともあるだろう。それでも相手に影響を与えようと思ったら、自分もその人から影響を受けなければならない。それが本当に相手を理解することなのである。
『7つの習慣』
『7つの習慣』の公的成功2に至る第4から第6の習慣の実践が難しい理由がここにあります。
相手を理解し、自分のことも理解してもらうためには、お互いに傷つけ合いながらも理解していくことが公的成功への道だからです。
だからこそ、私的成功である第1から第3の習慣が公的成功に先立つのだとコヴィー博士は仰っています。
だからこそ第1、第2、第3の習慣が基礎となるのである。それによって自分の中に変わらざる核、原則の中心が根づき、傷つきやすい部分を外にさらけ出しても、気持ちは少しも揺るがず、深く安心していられるのである。
『7つの習慣』
相手の不平不満に対して私たちができることは、私たち自身の軸を作り上げることからなのです。
「馬を水辺に連れていくことはできるが、水を呑ませることはできない3」と言われるように、私たちに他人を変えることはできません。
しかし、自分を変えることは、自分でできる努力です。
日々、私的成功の習慣を実践し、自立し、相手を受け入れる軸を整えることは、今この瞬間にでもできる努力です。
相手の不平不満にイライラするのではなく、自分のイライラを相手にぶつけるのでもなく、日々自分の影響の輪に集中することで、よりよいコミュニケーションを取れるようになりましょう。
7つの習慣(R)実践会では、書籍『7つの習慣』を読み、自分事に落とし込むワークを通じて、参加者の皆さんと一緒に私的成功から公的成功への道を歩むことができます。
参加者の中には、引きこもりの子供が就職したという人や、10年以上会話のなかった息子から誕生日を祝ってもらえたなど、自分の影響の輪に集中することで、周囲とのコミュニケーションを改善した事例がたくさんあります。
日々の生活の中で、誰かの話にイライラを感じることが多いのであれば、一度参加してみてください。
脚注
 Life Quest Alliance
Life Quest Alliance