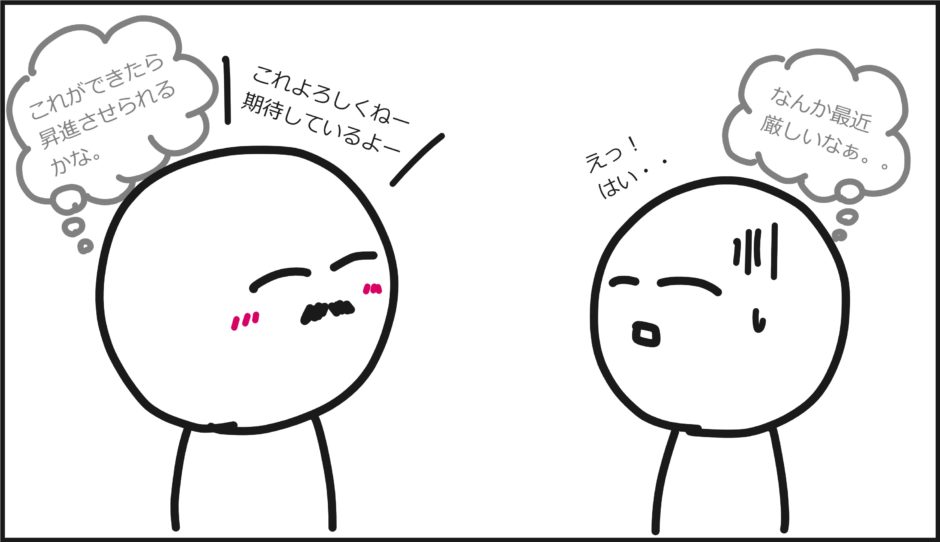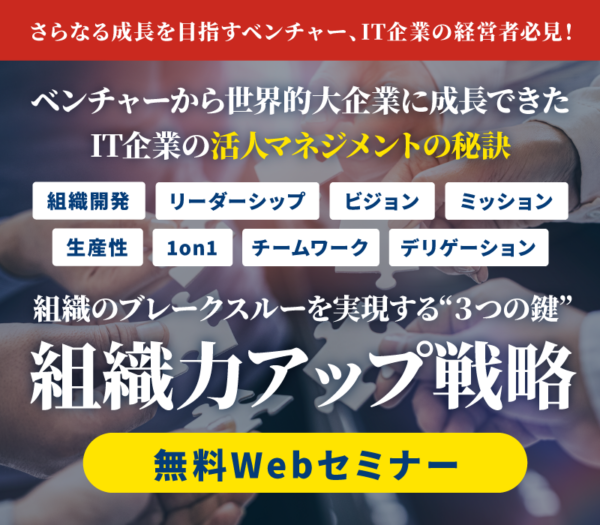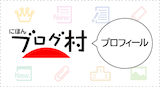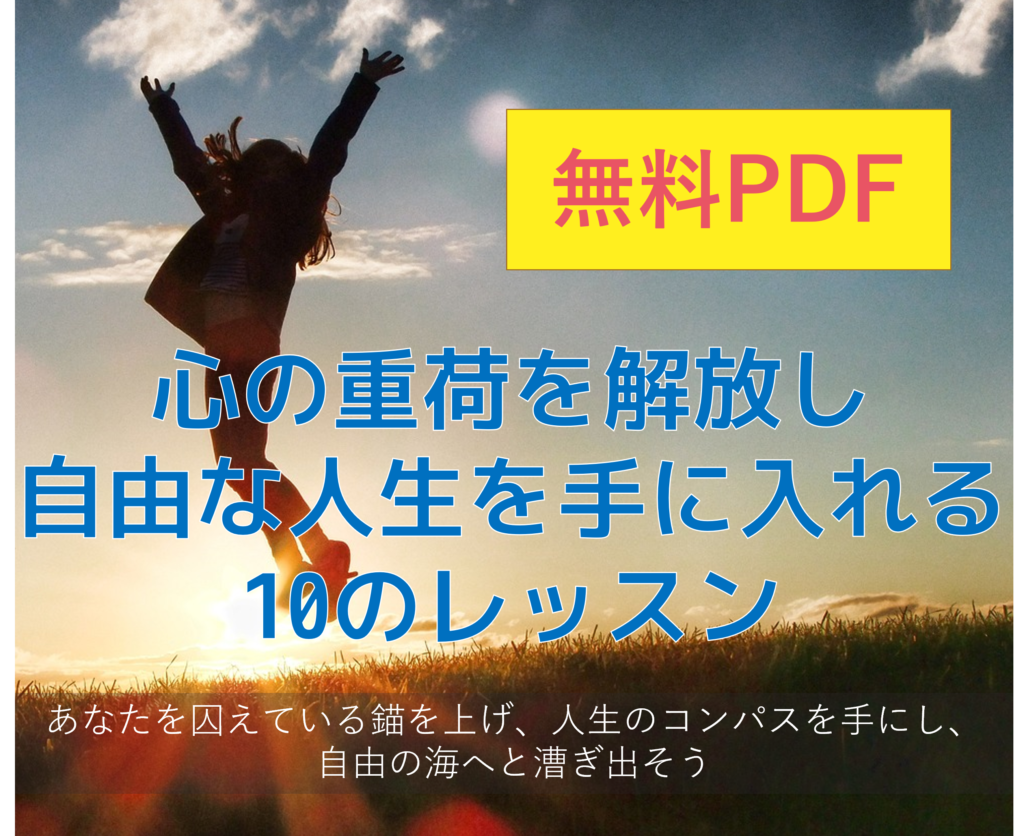部下が退職するという状況は、多くの経営者やマネージャが直面する現実です。
彼らが退職する理由は様々ですが、理由の一つに「自分の未来が見えない」というものがあるでしょう。
私が楽天で働いていた頃、ある同僚が会社を辞める決断をしました。
その理由は、ヘッドハンティングを受け、自分が本来やりたかった仕事に挑戦する機会が手に入ったからです。
興味深いことに、楽天からのカウンターオファーにも、同様の挑戦の機会が含まれていたとのこと。
今回の記事では、彼がそれでも退職を決めた理由から、部下を持つマネージャーとして、どのようなコミュニケーションが日常的に必要なのかを探求していきます。
彼が望んでいたキャリアパスは、以前から周囲にも知られていました。
彼の上司もこの方向性を認識しており、彼が所属していた組織もそのキャリアパスに沿って進化していたように見えました。
言い換えれば、彼が希望するキャリアは、転職せずとも築くことが可能だったはずです。
それにもかかわらず、彼は転職を選びました。
外部からのオファーがあったことも影響しているでしょうが、最も重要だったのは
「そのキャリアパスが、退職の意を伝えるまで明示されなかった」
点でした。
たとえ、上司が部下に対して未来のプランを持っていても、それが部下に伝わっていなければ、それは「部下からは見えない上司の期待値」となってしまいます。
上司が部下に与える様々なチャレンジも、その期待値が明示されていないと、部下は「なぜこの仕事を任されるのか?」や「なぜこんなに厳しいのか?」と疑問に感じるだけです。
このような誤解や不明瞭な状況を避けるためには、日常的なコミュニケーションでお互いの期待値を明確にしておくことが不可欠です。
具体的には、以下のようなポイントでお互いの認識を合わせておきましょう。
- あなたは部下に何を期待しているのか
- 部下はあなたや組織に何を期待しているのか
- 現在の組織で部下にどのような経験をさせてあげられるのか
- 部下がキャリアとしてどのような経験を積みたいと考えているのか
- その目標に向かってどのような挑戦が必要なのか
- 部下自身がどのような挑戦に興味を持っているのか
スティーブン・コヴィー博士の『7つの習慣』にも「全面的なデリゲーション」という概念があり、その中で「何が期待されているのかをお互いに理解し、納得しなければならない。」と述べられています。
1on1のセッションや日常の対話で、この原則を念頭に置き、部下に対する期待値や挑戦の方向性を明確に伝えましょう。
そして、もし現在の組織で部下に十分な挑戦の機会を提供できない場合は、異動や転職を積極的にサポートする度量を持つことも大切です。
このようにしてお互いが前向きに納得できれば、後任の選定や育成にも十分な時間を確保できるでしょう。
終身雇用がなくなり、転職でのキャリアアップが一般的になった今、経営者やマネージャーは部下の成長を真剣に考え、柔軟な対応が求められます。
もちろん、最初のステップは、現在の組織内でお互いが納得できる形で成長の機会を提供することをお忘れなく。
部下のやる気を引き出す1on1のやり方について、以下の無料Webセミナーで説明をしています。
効果的な1on1についてご興味があれば、ぜひ御覧ください。
(IT経営者向けと書かれていますが、セミナー部分は部下を持つ方にも役立つ内容です)
 Life Quest Alliance
Life Quest Alliance